実家を狙われる!高齢者のいる家庭の防犯対策とホームセキュリティ
「最近、親の家に見慣れない人がよく来ているみたいで心配…」
「『オレオレ詐欺』の電話が実家にかかってきたって聞いて、ゾッとしたわ」
「親が高齢だから、もしもの時、自分で対応できるか不安で…」
離れて暮らす親御さんを持つ方にとって、実家の防犯は常に頭の片隅にある大きな心配事ではないでしょうか。高齢者は、判断能力の低下や身体能力の衰えから、残念ながら犯罪者にとって狙いやすいターゲットとなってしまうことがあります。空き巣や強盗といった侵入犯罪はもちろんのこと、特殊詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺など)や悪質な訪問販売、さらにはつきまといや徘徊といった問題も後を絶ちません。
大切な親が、慣れ親しんだ実家で安心して穏やかに暮らせるよう、私たち家族ができることは何でしょうか?
この徹底解説記事では、あなたがご高齢の親御さんを守るために、実家の防犯対策を検討する上で知っておくべき、あらゆる情報を網羅的に提供します。
- 高齢者が狙われる背景と、主な犯罪手口の分析
- 高齢者のいる家庭に必須のホームセキュリティ機能と、その選び方
- 詐欺・悪質訪問販売対策に特化した見守り機能の活用術
- 離れて暮らす家族と連携する「見守りサービス」の重要性
- ホームセキュリティと合わせて行いたい、DIYでできる実家防犯対策
- 導入を検討する際の具体的な流れと、後悔しないための注意点
この記事を最後まで読めば、あなたは高齢者が狙われる手口を理解し、あなたの親御さんの実家に最適なホームセキュリティシステムを自信を持って選択できるようになるでしょう。そして、大切な家族と財産、そして何よりも心の平穏を守るための具体的な一歩を踏み出すことができます。あなたの「安心」を確かなものに変えるための第一歩を、ここから踏み出しましょう。
—

セコム(SECOM)
業界最大手の信頼感!
24時間365日、プロが見守る最上級の安心をあなたに。

アルソック(ALSOK)
ホームセキュリティの契約件数 125万件突破!
ホームセキュリティ販売実績はなんと30年以上

CSPセントラル警備保障
ご自宅の間取りや環境に合ったシステムをご提案
オーダーメイドに近い柔軟なプラン提案
2. 高齢者が狙われる背景と、主な犯罪手口を知る
高齢者が犯罪のターゲットにされやすい背景には、いくつかの共通する要因があります。その要因と、実際に高齢者がどのような手口で狙われているのかを理解することが、効果的な防犯対策の第一歩です。
2.1. 高齢者が狙われやすい背景
- 判断能力・身体能力の低下:
- 詐欺や悪質商法に対して、状況を冷静に判断する能力が衰え、騙されやすくなることがあります。
- 身体的な抵抗力が弱いため、侵入犯罪のターゲットにされやすい傾向があります。
- 咄嗟の判断や行動が遅れるため、緊急時の対応が難しい場合があります。
- 社会との接点の減少・孤独感:
- 近所付き合いが希薄になり、異変に気づかれにくくなることがあります。
- 孤独感から、親切を装って近づいてくる犯罪者に対し、警戒心が薄れることがあります。
- 自宅に現金や貴重品を保管する傾向:
- 現金を金融機関に預けず、自宅に保管する習慣がある高齢者も少なくありません。これが、空き巣や強盗のターゲットになる一因となります。
- 情報の変化への対応の遅れ:
- 新しい犯罪手口や、防犯に関する最新情報に疎い場合があります。
- 子どもが離れて暮らしているケース:
- 日中、あるいは常に一人で過ごしていることが分かると、犯罪者に狙われやすくなります。子どもが遠方に住んでいる場合、すぐに駆けつけられないという不安も生じます。
2.2. 高齢者を狙う主な犯罪手口
高齢者が被害に遭いやすい犯罪は多岐にわたりますが、特に注意すべき手口を挙げます。
2.2.1. 特殊詐欺(振り込め詐欺)
- オレオレ詐欺: 親族を装い「(自分だけど)携帯をなくした」「お金が必要」などと電話をかけ、現金をだまし取る手口。
- 還付金詐欺: 公的機関(税務署、市役所など)を装い、「医療費の還付金がある」などと電話をかけ、ATM操作を指示して現金を振り込ませる手口。
- 架空請求詐欺: 未払い料金がある、ウイルスに感染したなどと嘘を言って、現金を要求する手口。
- 特徴: 電話やインターネットを主な手段とし、高齢者の判断能力や情報への疎さに付け込みます。多くの場合、すぐに振込を指示するなど、考える時間を与えないように仕向けてきます。
2.2.2. 悪質な訪問販売・点検商法
- 不必要な工事や高額な契約: 屋根の点検、床下のシロアリ駆除などと称して、不必要な工事を高額で契約させたり、根拠のない健康食品を売りつけたりする手口。
- 押し買い: 「不用品を買い取る」と言って家に入り込み、安価で金品をだまし取る手口。
- 特徴: 強引な勧誘、長時間居座る、断ってもなかなか帰らないなど、高齢者が断りきれない状況を作り出します。
2.2.3. 侵入窃盗(空き巣・強盗)
- 在宅確認: インターホンを鳴らしたり、電気メーターをチェックしたりして、在宅しているか、一人暮らしであるかを確認します。
- 無締まり侵入: 短時間の外出や、庭での作業中に、鍵がかかっていない玄関や窓から侵入します。高齢者は戸締まりを忘れやすい傾向があります。
- 施錠破壊: ピッキングやバールなどを使って鍵を破壊し、侵入します。
- 強盗: 在宅中の高齢者を脅し、金品を奪う手口。身体的危害を加えるケースもあり、非常に危険です。
2.2.4. 不審者によるつきまとい・声かけ
- 特定の高齢者の行動パターン(散歩の時間、外出の頻度など)を把握しようと、つきまといや徘徊をする者。
- 「道に迷った」「水を分けてほしい」などと声をかけ、警戒心を解かせ、家に入り込もうとするケースもあります。
—
3. 高齢者のいる家庭に必須!ホームセキュリティの主要機能と選び方
高齢者のいる家庭の防犯対策は、侵入犯罪対策だけでなく、特殊詐欺や悪質訪問販売への対応、そして万が一の体調不良や事故時の見守りまで、多角的な視点が必要です。ここでは、高齢者を見守り、守るためのホームセキュリティ機能と、その選び方を解説します。
3.1. 訪問者を「確認・威嚇・拒否」する玄関セキュリティ
高齢者を狙う犯罪者の多くは、まず玄関から接触を試みます。玄関での対策が非常に重要です。
3.1.1. スマートインターホン(録画・遠隔応答・自動録画機能付き)
- 効果: 来訪者の顔をモニターでしっかり確認でき、録画機能があれば後で誰が来たかを確認できます。最も重要なのは、離れて暮らす家族がスマートフォンのアプリでリアルタイムに映像を確認し、遠隔で応答できる機能です。これにより、親御さんが直接ドアを開けずに、家族が不審者や悪質な訪問販売業者に対応できます。
- 選び方: 広角レンズで来訪者の全身を捉えられるもの、夜間でも鮮明な映像が得られる暗視機能付きを選びましょう。自動録画機能があれば、親御さんが操作しなくても履歴が残ります。
3.1.2. 玄関カメラ・人感センサーライト
- 効果: 玄関や敷地内に不審者が入ってきた際に、自動で録画を開始し、明るい光で威嚇します。親御さんが気づかない間に、不審者がうろついていた場合でも、映像で確認できます。
- 選び方: 高画質で夜間対応のものが必須です。人感センサーライトは、音量が大きく、近隣にも聞こえるような警報音や音声アナウンス機能があるものがより効果的です。
3.1.3. スマートロック(遠隔施錠・解錠・履歴確認機能付き)
- 効果: 鍵の閉め忘れを防止し、離れて暮らす家族が遠隔で施錠状況を確認・操作できます。もし親御さんが鍵を閉め忘れていても、家族がスマートフォンで施錠できるため安心です。また、親御さんの入退室履歴を確認することで、日中の行動把握にも役立ちます。
- 選び方: 高齢者でも操作しやすいシンプルなデザインで、工事不要で取り付け可能なタイプ(賃貸でも安心)がおすすめです。
3.2. 侵入を「検知・威嚇・通報」する防犯システム
万が一、不審者が侵入してきた場合でも、速やかに検知し、プロが対応できるようにします。
3.2.1. 開閉センサー(窓・ドア)
- 効果: 玄関ドアや窓が開けられた瞬間に検知し、大音量の警報を発すると同時に、警備会社へ自動通報します。高齢者が気付かない間に侵入されても、プロが速やかに対応してくれます。
- 選び方: 侵入経路となりうる全ての窓やドアに設置することが推奨されます。特に掃き出し窓や、人目につきにくい窓は重点的に対策しましょう。ワイヤレスで電池寿命の長いものがメンテナンス負担を減らします。
3.2.2. 空間センサー(人感センサー)
- 効果: 開口部からの侵入を検知できなかった場合でも、室内に侵入者が入ってきたことを感知し、警報を発し、警備会社へ通報します。これにより、不審者が室内の奥まで到達する前に検知し、高齢者の安全を確保する時間を稼ぎます。
- 選び方: リビングや廊下など、侵入者が必ず通過するであろう場所に設置します。誤作動を防ぐためのペット識別機能や、高齢者の日常の動きを妨げない設置場所が重要です。
3.2.3. 緊急通報ボタン(非常ボタン・サイレントアラーム機能付き)
- 効果: 在宅中に不審者と鉢合わせしてしまった場合や、体調不良で動けない場合など、直接通報が難しい状況でも、ボタン一つで警備会社へ緊急通報できる機能です。音を出さずに通報できる「サイレントアラーム」機能は、不審者に気づかれずに助けを求めるために非常に重要です。
- 選び方: 高齢者が常に身近に置けるよう、ペンダント型や据え置き型など、複数のタイプを検討しましょう。寝室の枕元、リビングのソファの脇、トイレや浴室など、緊急時にすぐに手の届く場所に複数設置し、操作方法を練習しておくことが必須です。
3.3. 離れて暮らす家族も安心の「見守りサービス」
防犯だけでなく、高齢者の日常生活の異変を察知し、安否確認を行う機能は、離れて暮らす家族にとって最も重要な機能かもしれません。
3.3.1. 安否確認センサー(生活リズムセンサー)
- 機能: 一定時間、室内の人感センサーに動きがない、電気の使用がない、あるいは特定の家電(冷蔵庫、電子レンジなど)の使用がないといった状況を検知すると、自動的に離れて暮らす家族や警備会社へ通知されるサービスです。
- 効果: 高齢者の急な体調不良や、転倒などにより動けなくなった場合など、異変を早期に察知し、迅速な対応に繋がります。親御さんの負担にならずにさりげなく見守れるため、プライバシーにも配慮できます。
- 選び方: 親御さんの生活スタイルに合わせて、検知する時間帯やセンサーの感度を調整できるものが望ましいです。
3.3.2. 火災・ガス漏れ・COセンサー連携
- 機能: 火災報知器やガス漏れセンサーとホームセキュリティが連携し、異常を検知した際に警報音を発すると同時に、警備会社へ自動通報します。
- 効果: 高齢者が異変に気づかなかったり、対処できなかったりした場合でも、自動的に警備会社が状況を確認し、必要に応じて消防やガス会社へ連絡、または警備員が駆けつけるため、早期対応が可能です。
- 選び方: 信頼性の高いセンサーであるか、定期的な点検や電池交換が容易かを確認しましょう。
3.3.3. 24時間365日のプロの「駆けつけサービス」
- 効果: センサーが異常を検知したり、緊急通報ボタンが押されたりした場合、訓練された警備員が現場に急行し、状況確認と適切な対処を行います。不審者への威嚇、警察・消防への通報、そして高齢者の安全確保までを一貫して行ってくれます。これは、離れて暮らす家族にとって、最大の安心材料となります。必要に応じて、親族への連絡も代行してくれます。
- 選び方: 警備会社の拠点数と駆けつけ速度は最も重要です。セコムやALSOKのような大手は、全国に多くの拠点を持ち、「最短10分以内」などの迅速な駆けつけを謳っています。実際に契約前に、実家から警備拠点がどこにあるか、おおよその駆けつけ時間を確認しておくと良いでしょう。
—
4. 高齢者詐欺・悪質訪問販売対策に特化した見守り機能の活用術
高齢者を狙う詐欺や悪質訪問販売は巧妙化しており、物理的な防犯だけでは防ぎきれないことがあります。ホームセキュリティの見守り機能を活用して、これらの被害から親御さんを守るための具体的な方法を紹介します。
4.1. スマートインターホンで「詐欺・訪問販売」を撃退
玄関での最初の接触が、詐欺や悪質商法の入り口となることが多いため、インターホンの活用は非常に重要です。
- 遠隔応答機能の活用:
- 離れて暮らす家族がスマートフォンのアプリで、実家のインターホン越しの来訪者と直接会話できる機能は、高齢者詐欺・訪問販売対策の切り札です。
- 親御さんには「知らない人が来ても、インターホンには出ないで、電話が鳴ったら私に連絡してね」と伝えておきましょう。
- 親御さんから電話がかかってきたら、家族がスマートフォンでインターホンに応答し、「〇〇です。何かご用でしょうか?」「セールスならお断りします」などと毅然と対応することで、詐欺師や悪質業者を撃退できます。
- 「親が在宅しているかのように装う」ことも可能です。これにより、一人暮らしの高齢者だと悟られにくくなります。
- 自動録画機能の活用:
- インターホンが鳴ると自動的に録画を開始する機能があれば、親御さんが操作しなくても、誰がいつ訪ねてきたかの記録が残ります。
- 不審な人物の顔や会話内容が記録されるため、後で警察への情報提供や、家族での状況把握に役立ちます。
- 「録音機能付き電話機」との併用:
- ホームセキュリティの直接的な機能ではありませんが、自宅の固定電話に、通話内容を自動で録音する機能付き電話機を導入することも強く推奨されます。「この電話は詐欺対策のため録音しています」という自動音声が流れるだけでも、詐欺師は警戒し、電話を切ることが多いです。
4.2. 見守りセンサーで「異変」を察知し、家族で連携
高齢者の生活リズムの異変は、詐欺被害に遭っているサインである可能性も考えられます。
- 生活リズムセンサー(安否確認センサー)の活用:
- 一定時間、親御さんの生活活動(動きや家電の使用など)が検知されない場合に、離れて暮らす家族に通知が届くサービスです。
- 普段と違う行動パターンが検知された場合、詐欺被害に遭って困っている、あるいは心身に異変が起きている可能性を早期に察知し、電話連絡や、必要であれば警備員の駆けつけを依頼するなど、迅速な対応に繋がります。
- 家族への通知機能の設定:
- ホームセキュリティシステムが何らかの異常を検知した際、警備会社への通報だけでなく、離れて暮らす家族のスマートフォンにも通知が届くよう設定しておくことが重要です。
- これにより、家族はリアルタイムで実家の状況を把握し、連携して対応することができます。
4.3. 定期的なコミュニケーションと情報共有
システムだけでなく、家族間の密なコミュニケーションが最も重要です。
- 「知らない人にはドアを開けない」「不審な電話はすぐに切る」の徹底:
- 親御さんには、口酸っぱくなく、しかし繰り返し、これらの防犯ルールを教えてあげましょう。
- 具体的な手口(「還付金がある」「息子を名乗る」など)を伝え、注意を促すことも大切です。
- 「困ったことがあったら、すぐに連絡する」という関係作り:
- 親御さんが、不安なことや困ったことがあったら、遠慮なく子どもに連絡できるような信頼関係を築いておくことが、詐欺被害を防ぐ上で非常に重要です。
- 定期的に電話をかけたり、訪問したりして、親御さんの様子を伺い、不審な出来事がなかったか話を聞いてあげましょう。
—
5. ホームセキュリティと合わせて!DIYでできる実家防犯対策
ホームセキュリティは非常に強力なツールですが、それだけで万全というわけではありません。ホームセキュリティの機能を補完し、より強固な防犯体制を築くために、DIYでできる実家防犯対策も合わせて行いましょう。特に、高齢者でも無理なくできる、シンプルで効果的な対策が重要です。
5.1. 物理的な対策で「見せる防犯」と「侵入困難化」
不審者は、防犯意識が高い家や、侵入に手間がかかる家を避ける傾向があります。
- 防犯カメラや警備会社のステッカーの設置:
- 本物の防犯カメラはもちろん、ダミーカメラでも、目立つ場所に設置することで強い抑止効果があります。
- 警備会社と契約している場合は、そのステッカーを玄関や窓など、複数箇所に貼ることで、不審者に「この家はセキュリティ対策済みだ」とアピールできます。
- 人感センサーライトの設置:
- 玄関、庭、駐車場、裏口など、夜間に不審者が隠れやすい場所や侵入経路となりうる場所に設置し、不審者が近づくと自動で点灯するようにします。急な光は不審者を驚かせ、見つかるリスクを感じさせます。
- 高齢者自身の夜間の転倒防止にも役立ちます。
- 防犯砂利の敷設:
- 庭や家の周囲に敷くことで、足音が大きく鳴り、侵入者に心理的なプレッシャーを与えます。夜間の音は特に響きやすく、不審者を退散させる効果が期待できます。
- 見通しの良い環境作り:
- 高い塀や植木は剪定し、家の周囲の見通しを良くすることで、不審者が隠れて作業できる場所をなくします。死角を減らすことが重要です。
- 高齢者自身が庭の手入れをするのが難しい場合は、家族が手伝ってあげましょう。
- 鍵の強化:
- ワンドア・ツーロック: 玄関ドアに鍵を2つつけることで、侵入に時間がかかり、諦める可能性が高まります。
- ピッキングに強い鍵への交換: 古い鍵の場合は、ピッキングに強いディンプルキーなどへの交換を検討しましょう。
- 窓への補助錠の設置: 窓にも簡単に取り付けられる補助錠を設置し、二重の施錠を徹底しましょう。高齢者でも簡単に操作できるタイプを選びます。
- 防犯フィルムの貼付:
- 窓ガラスに防犯フィルムを貼ることで、ガラスを割られにくくし、侵入に時間をかけさせます。高齢者が誤ってガラスを割った際の飛散防止にもなります。
5.2. 行動習慣と意識で「見せない防犯」
不審者に「狙う価値がない」「留守でない」と思わせるための行動習慣も大切です。高齢者自身が負担なくできる工夫が重要です。
- 留守を悟られない工夫:
- 郵便物や新聞の溜まり具合: 長期不在の際は、郵便配達や新聞の一時停止サービスを利用しましょう。日頃から郵便受けをこまめにチェックし、溜めないようにする。離れて暮らす家族が定期的に確認しに行くのも良いでしょう。
- タイマー付き照明・家電: 留守中も定時に室内の照明やテレビを点灯させ、生活しているように見せかけることで、不審者に留守を悟られにくくします。ホームセキュリティのアプリから遠隔操作できる機能も活用できます。
- 戸締まりの徹底:
- 短時間の外出でも、全ての窓やドアの施錠を徹底するよう、親御さんに繰り返し伝えましょう。忘れがちな場合は、戸締まりを促す貼り紙をするなどの工夫も有効です。
- 近所付き合い:
- 日頃から近所の人と挨拶を交わし、不審者に気づいてもらいやすい環境を作ることが大切です。地域の防犯活動にも積極的に参加できるのであれば、協力しましょう。
- 長期不在の際に、新聞や郵便物の取り込み、植木への水やりなどを近所の方にお願いできる関係性を築いておくと、より安心です。
- 個人情報の管理:
- 表札にフルネームを書かない、インターホンに「セールスお断り」と表示するなど、個人情報を安易に公開しない工夫も必要です。
- 電話番号も、安易に教えないよう親御さんに伝えましょう。
—
6. 導入までの具体的な流れと、後悔しないための注意点
高齢者のいる実家のためにホームセキュリティを導入する際、契約から設置、そして利用開始までの流れを把握しておくことで、スムーズに進めることができます。また、後悔しないための重要な注意点も確認しておきましょう。
6.1. 導入までの具体的な流れ
- 家族で相談・ニーズの明確化:
- まずは家族(親御さんと、離れて暮らすお子さんなど)で、どのような防犯対策や見守りが必要かを話し合いましょう。「詐欺対策を強化したい」「転倒時の安否確認が不安」「空き巣対策をしたい」など、具体的なニーズを明確にします。
- 親御さんの意見や希望も尊重し、無理なく導入できるシステムを検討することが大切です。
- 情報収集・比較検討:
- セコムやALSOKなど大手警備会社の公式サイトで、提供されている高齢者向けの見守り・防犯プランや機能、料金体系について大まかに情報を集めましょう。
- 複数の会社の資料請求を行い、機能、サポート体制、料金などを比較検討します。
- 無料相談・現地調査・見積もり:
- 気になる警備会社に連絡し、無料相談を申し込みます。多くの会社は、専門の担当者が実家を訪問し、現地調査を行います。
- 担当者は、住居の間取り、窓やドアの配置、周辺環境、そして特に高齢者の生活を考慮した懸念点(死角、玄関前の状況、危険な場所、親御さんの生活リズムなど)を詳しくヒアリングし、最適なプランや必要な機器の提案を行います。この段階で、親御さんの生活スタイルや、家族の心配事を積極的に伝え、専門家としての意見を求めましょう。
- 提案内容に基づき、初期費用や月額料金を含めた詳細な見積もりが提示されます。
- 契約内容の確認・契約:
- 提示された見積もりとサービス内容に納得したら、契約手続きに進みます。
- 契約書の内容を隅々まで確認することが非常に重要です。特に、月額料金の内訳、契約期間、解約条件、違約金、誤作動時の対応、保証期間、そして緊急時の警備員の具体的な対応(高齢者への配慮、警察への通報、親族への連絡など)について、後でトラブルにならないよう、不明な点は全て質問し、明確にしておきましょう。
- 親御さんの名義で契約する場合でも、お子さんが同席し、内容をきちんと理解・確認してあげましょう。
- 工事・設置:
- 契約後、専門スタッフが訪問し、システムの設置工事を行います。工事時間は住居の規模や設置する機器の種類によって異なりますが、半日~1日程度が目安です。
- 工事中に、機器の操作方法や緊急時の対応について説明を受けます。実際に操作してみて、分からないことがあればその場で質問し、必ず使い方を習得しましょう。特に、スマートインターホンの操作方法、カメラ映像の確認方法、緊急通報ボタンの場所と使い方などは、親御さんが理解できるように丁寧に説明し、一緒に練習してあげることが重要です。
- 運用開始・定期的な見直し:
- システムの設置が完了すれば、すぐに運用を開始できます。
- 運用開始後も、定期的に動作チェックを行い、センサーの感度調整や、親御さんの生活スタイルの変化に合わせて設定を見直すことが、システムを最大限に活用するために重要です。
- 困ったことがあれば、24時間365日のカスタマーサポートを活用しましょう。
6.2. 後悔しないための重要チェックポイント
高齢者のいる実家のためにホームセキュリティを導入して後悔しないために、以下の点を特に注意して確認しましょう。
- 7.2.1. 必ず複数社と比較検討する
- セコム、ALSOKといった大手警備会社は高齢者向けの見守りサービスに強みがありますが、料金、機能、サポート体制、駆けつけ速度など、各社で特徴が異なります。
- 必ず複数の会社の資料請求や見積もりを取り、料金、機能、サポート体制、駆けつけ速度などを総合的に比較検討することで、親御さんのニーズと予算に最も合った最適なサービスを見つけられます。特に、詐欺・訪問販売対策に有効なスマートインターホン、安否確認センサー、緊急通報ボタンの操作性と対応体制、そして万が一の際の警備員の具体的な対応を重点的に確認しましょう。
- 7.2.2. 「総額」で料金を比較する
- 初期費用が安いからといって安易に飛びつかず、月額料金と合わせて、契約期間全体(例:5年、10年)で支払う「総額」で比較しましょう。特に、買い取りプランとレンタルプランでは、初期費用と月額料金のバランスが大きく異なるため、長期的な視点での比較が重要です。
- 親御さんの安全に必要な機器(スマートインターホン、安否確認センサー、緊急通報ボタンなど)を追加した場合の総費用も必ず確認してください。
- 7.2.3. 親御さんの負担にならないかを確認する
- 新しいシステムを導入することに対して、親御さんが操作に戸惑ったり、ストレスを感じたりしないかを確認しましょう。
- 操作がシンプルで分かりやすいか、機器のメンテナンスが容易か、誤作動が少ないかなど、高齢者への配慮がされている製品を選ぶことが重要です。
- 親御さんのプライバシーを尊重し、カメラの設置場所や運用方法について、事前にしっかりと話し合い、同意を得てから導入しましょう。
- 7.2.4. 緊急通報ボタンの操作性と設置場所を親御さんと一緒に確認する
- いざという時に迷わず操作できるよう、操作が簡単で分かりやすいものを選び、寝室の枕元、リビングのソファの近く、トイレや浴室など、緊急時にすぐに手の届く場所に複数設置されているかを確認しましょう。
- 実際に親御さんに操作方法を教え、何度か練習させておくことが重要です。音が出ない「サイレントアラーム」機能の有無も確認しましょう。
- 7.2.5. 離れて暮らす家族との連携方法を確認する
- 警備会社からの異常通知が、誰のスマートフォンに届くのか、複数人に通知できるのか、通知の種類は選べるのかなどを確認しましょう。
- 緊急時に家族が遠隔で状況を確認できる(カメラ映像の確認など)機能があるかどうかも重要です。
—
8. まとめ:高齢者のいる実家は「見守り」と「安心」のセキュリティで守る
この「実家を狙われる!高齢者のいる家庭の防犯対策とホームセキュリティ」ガイドを最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
高齢者のいる実家は、残念ながら詐欺や空き巣、悪質な訪問販売など、様々な犯罪のターゲットになりやすい現状があります。離れて暮らす家族にとって、親御さんの安全と安心は、常に尽きない心配の種です。
ホームセキュリティは、物理的な防犯対策だけでなく、「スマートインターホンによる不審者・詐欺対策」「安否確認センサーによる見守り」「緊急通報ボタンと連携したプロの警備員による迅速な駆けつけ」といった、高齢者のいる家庭に特化した多角的な見守り・防犯機能を提供します。これにより、親御さんの日常生活の異変を早期に察知し、万が一の事態にも迅速に対応できる体制を整えることができます。
セコムやALSOKといった大手警備会社は、その信頼性と実績、そして高齢者向けに特化した充実したサービスで、親御さんの安全を強力にサポートしてくれるでしょう。また、システム導入と合わせて、物理的な防犯対策(鍵の強化、人感センサーライトの設置など)や、家族間の密なコミュニケーション、そして親御さんへの防犯意識の啓発を継続的に行うことが、何よりも重要です。
この記事が、あなたが大切な親御さんの実家を守り、家族全員が「安心」を手に入れるための一助となれば幸いです。あなたの家族の平穏な毎日を応援しています。
高齢者のいる実家の防犯・見守りを強化したい方へ
このガイドでホームセキュリティに興味を持たれた方は、ぜひ下記の公式サイトから詳細な情報をご確認ください。
無料の資料請求や、オンライン・電話での無料相談も可能です。あなたの疑問や不安を解消し、最適なプラン選びのためのサポートを受けることができます。
あなたの「安心」を確かなものにするために、今すぐ一歩を踏み出しましょう。




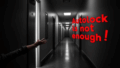
コメント